うちがわに広がりをもつもの
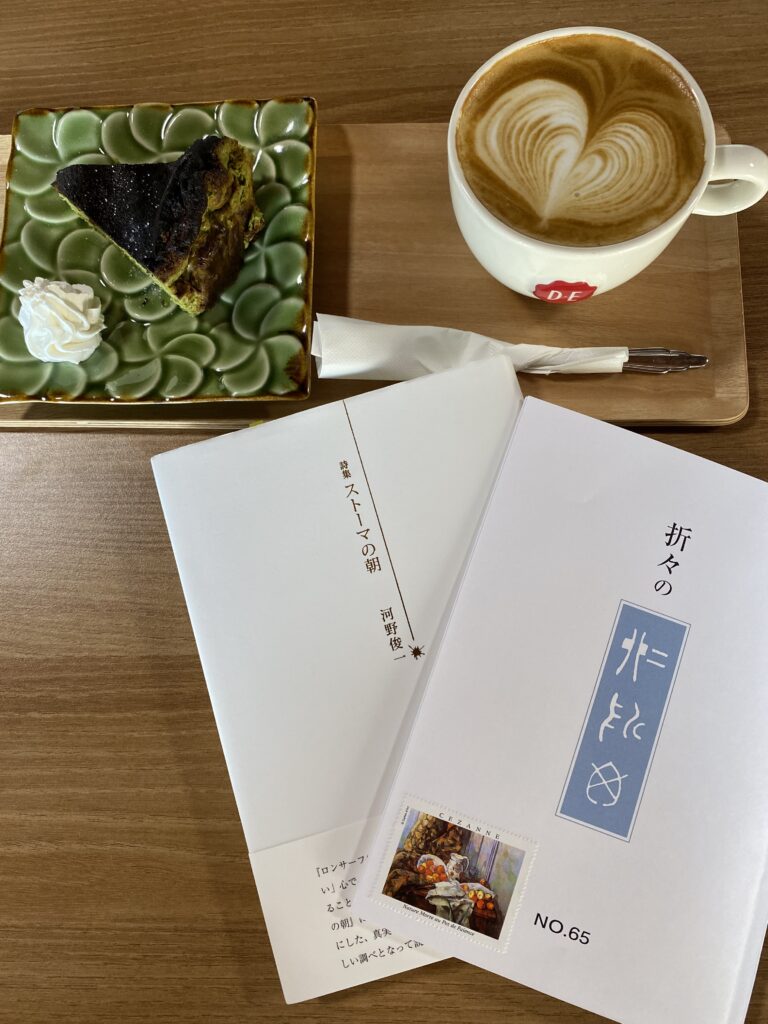
折々の詩誌NO.65 2025年7月1日刊
今回ははじめて書評を載せています。
河野俊一さん詩集『ストーマの朝』の書評を綴っています。
~うちがわに広がりをもつもの~
「おはよう/と目がさめ/おはよう/と返す/目ざめれば/
まぶしく言葉が立ち上がる/ぐずぐずしないよ/薬は飲んだの/
いっぱい食べなさい/と言える」
(「おはよう」)
「いつまでがこどもで/いつからがおとなか/思いにくれなずみ/
おっとりと頬杖をつくと/夕日が落ちてゆく」
(「となりあわせの」)
朝のようにまぶしい我が子の生の輝きを抱き締めながら、病を抱えて生きる子に大人びた横顔を見つけてしまう。親は夕日を知る痛みを隠したまま、子を抱き締める。
*
「小さな娘から/お菓子屋を開くように仰せつかった/
積み上げた本と/敷いた布団の間に/お菓子屋を設ける」
(「失業」)
布団の上でも子どもは子どもであることを決して忘れてはいない。病気であることを親と子ともに忘れて過ごすひととき。日常の一片を見つめる詩は、生まれては消えるその時間を永遠に代えてゆく。
*
「おまえの中には/しめやかな小さな森が育ち始め/私の中には/
沈黙に耐える耳が/生まれようとしていたからだった」
(「もうあの頃のおまえは」)
「ながれだしたものを受けとめるのは/きっと/
親と子の間に横たわる/狭くかぐわしい溝だ」
(「新しい礼服」)
「いのちの最後の四十分間/俺はおまえの脚をさすり続けて/
同じ言葉ばかりを/繰り返していたのだった/
大丈夫だよ と/大好きだよ の/ふたつだけ」
(「貧しい言葉」)
生と死の痛みは、いのちの愛しいかなしみである。鼓動する生の時間のなかに、背中合わせのように透明な死は一緒に生きている。そして死は、最後の息を包み込み、生を静かに眠らせる。
「生は死のページを透かせば/薄く見える鏡文字/
寄り添うというものでもないのだが/
目配せくらいはする/息が見える寒い夜」
(「追熟」)
「穏やかな朝」は河野さんの亡き娘・晃子さんのまなざしとなり父に語りかける。
「お父さん/何が一番大変でしたか/
お葬式でも終わって/穏やかな朝が繋がったら/
お参りするときにでも/そっと教えてね」
(「穏やかな朝」)
*
「かなしみとは/そんな家のようなものだ/
光をとおして/うちがわに広がりをもつもの/
そしてその中で/空気だけを刻んでいる時計が/固くうつむく」
(「美しい家」)
「美しいのは病院の窓だ/しかし/
外から眺めるのか/内から眺めるのかで/
通り過ぎるものの速さが/違って見える夕方もある」
(「生きること 窓」)
美しい家で夜明けを待ち、美しい窓から夕日を見つめる人は、朝を「おはよう」と抱きしめている。
(『ストーマの朝』 河野俊一 2024年6月30日発行 土曜美術社出版販売)